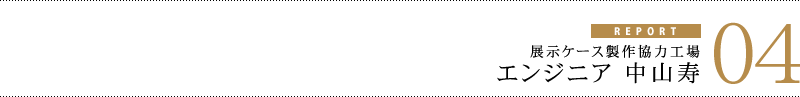美術品や歴史的価値の高い品物を展示する展示ケースには、モノを美しく「見せる」ことと、モノを劣化させず「守ること」の二律背反する課題が常に課せられています。
この難しい課題に日々取り組んでいるのが、コクヨファニチャーの展示ケース設計部署MUSEUM TEAMと協力工場のエンジニアたち。
匠レポートでは、THEORiAを支える匠たちとして、展示ケース製作に情熱を注ぐエンジニアたちをご紹介していきます。
掲載している内容は取材当時のものです。
展示ケース製作の仕事に携わって10年、中山寿の仕事は展示ケースの設計だ。中山は自分の仕事を“あいだをとりもつ仕事”と説明する。
「僕らの仕事は、まずコクヨさんから『こういう物件がある』という話から始まります。その段階で、コクヨさんはすでにお客様(施主や設計事務所など)の要望をお聞きして、大枠の設計図を描いているので、僕らはその図面をもとに、実際のケースを仕上げるために必要な納まり図やバラ図と呼ばれる製作図面を描きます。製作図面を描くには、お客様の要望と、コストや技術的なことのすり合わせが必要なので、工場や現場の作業者と『できる・できない。そこを何とか…』みたいな話をしながら、ネジ1本から図面を描き起こしていくんです」。
展示ケース製作に必要なあらゆるパーツを、ネジ1本、部品1つ、1枚ずつ図面に描き起こす――。想像するだけで、何とも気の遠くなるような作業だが、緻密に設計された製作図面がなければ、実際の展示ケースは仕上がらない。当然、設計にかける時間は、半端ではない。取材時、ちょうど終盤にさしかかっていた根津美術館の壁面ケースの仕事は、昨年の9月末から図面を描きはじめ、実に半年もの間、図面を描き続けていたという。
「やはり設計にはとても時間がかかります。例えば、設計事務所から『ネジの取付部のアキは、できるだけ見せたくないから5mmにおさえたい』と注文があったとしますよね。それに対して、僕たちとしては作業性を考慮して15mmアキが欲しいという場合、ギリギリどこまで詰められるか、現場やコクヨさんと話し合って、『じゃあ、ここは厳しいけど、10mmでいこう』というように、詳細を決めていくんです。設計事務所は、意匠に対する要求がとても高いので、見えるところの目地はできるだけ小さく細く、2mmとか1mm単位のオーダーが入ります。でも、すべてを小さく目立たないようにとなると、作業性やコストの問題だけじゃなく、強度や納める難しさが出てきますので、どこで折り合いをつけるか、いつもギリギリのところでのせめぎあいになりますね」。

図面が描きあがれば、次は工場や現場の作業者と、実際の展示ケースに仕上げていく作業が待っている。作品を守りながら、見せながら、しかも、使いやすさも求められる展示ケース製作の世界。中山は、ユーザーの気持ちを作業者へ伝えるためにも、できるだけ現場に通うようにしているという。
「展示ケース製作はすごく特殊なので、普段、一般建築の仕事をしている作業者からすると、『何でそこまで…』と戸惑うところがあると思うんです。側にいれば、そういうとき『時間がかかっても、そうしないとお客様には満足してもらえないんです』と、説明できますよね。間違いにもすぐ気づけますし…。もちろん最初に『こういう風にしてください』と伝えますし、それでやってもらわないといけない部分もあるんですが、やっぱり図面だけではうまく伝わらない場合もあるので」。
しかも、工事の仕事は一旦作業が進んでしまうと、なかなか後戻りができない。ミスは小さな芽のうちに摘み取らないと、あとで大変なことになる。だからこそ、横着せずに現場に足を運び、作業を見ることも大切だと中山は言う。
「ここはちょっとマズイ…、と感じたところは、必ず検査で引っかかります(笑)。自分が買う立場になれば当然のことですが、検査のときは皆さん『これでもか!』というぐらい厳しい目でチェックをされるので。ですから、この仕事は、ごまかしもできないし、横着もできない。一歩一歩着実に進むしかない、近道のない仕事なんです」。

学校では機械を学び、実は、ミュージアムにも建築にも縁がなかったという中山が、はじめて展示ケースの仕事に関わったのは、愛媛県宇和島の伊達博物館の改修工事。初仕事は、自分の未熟さに悔しさが残るせいか、やはり強烈に印象に残っているという。
「工場研修を終えて、入社2年目に設計の仕事に携わって、すぐにコクヨさんからお話があったんです。当時は、まだ建築のこともよく知らなかった上に、展示ケースの仕事といえば、ものすごい精度を求められるので、難しかったですね。あの頃はホントに右も左もわからず、それこそガキの使いみたいな感じで、図面をひいて、現場につないで『できるか、そんなモン』って怒られたり、できたものに対しては『こんなんじゃアカン』って言われたり。皆さんにビシビシと指導していただきました(笑)。あの時は本当に毎日のたうちまわってましたね。でも、不思議と『辞めたい』とは思わなかったんですけど」。
それから10年。中山は全国各地で展示ケース製作に関わり、2007年には関係者から高い評価を受けたサントリー美術館の島ケース、そして現在(取材時)は、根津美術館の壁面ケース製作と、着実に経験を積み上げている。
中山が“鉄人”と呼ぶ、コクヨファニチャーのエンジニア山内も、中山の成長ぶりには目を見はる。「彼がすごいのは、設計から現場管理から作業・メンテナンスまで、全部自分でできるところ。性格的に、『オレが、オレが』というタイプではないけれど、やっぱり最初から飛び抜けていましたよね。それに、10年でここまで力をつけるっていうのは、並大抵じゃない。相当見えないところで努力をしているはず」(山内)。
今では同じ仕事をする協力工場の山下(匠シリーズ02)と並び、中山は展示ケース製作のエンジニアとして、なくてはならない存在になっているという。
しかし、そんな中山に『こんなこと、ホントにできるんですか?』と弱音を吐かせた仕事がある。サントリー美術館の島ケースだ。
「最初、コクヨさんから計画を見せていただいたとき、何かの冗談かと思ったんです。だって、“何もない展示ケースが欲しい”というオーダーでしたから。でも、1つ1つ『この目地はなくそう』『この金物は見えないようにしよう』と要素を削ぎ落としていって、最終形としては、本当にガラスと床面とパネルしかないケースが仕上がった。当然のことですが、性能も有していて…。サントリー美術館の仕事は、『やって、やれないことはない』ということを、つくづく実感した仕事でしたね」。

現在、手がけている根津美術館の壁面ケースも、電動で展示ケースの奥行きを調整できたり、展示ケースの前面パネルを取り外しできたり、さまざまな工夫と最新の技術が取り入れられている。
「お客様も設計事務所の方も展示ケースに対して並々ならぬこだわりをお持ちなので、オーダーに応えるのは非常に難しいです。品質的にも製作技術の面でも限界近くギリギリのハイレベルなところでやっているので…。でも、どんなに難しいオーダーも、『できない』とは思いたくない。厳しい要望に応えることで達成感もあるし、次へ行けるわけですから」。
「こんなことを言うとおかしいかもしれませんけど」と前置きして、中山はこうも続けた。「できるか・できないかの瀬戸際あたりで、あたふたとのたうちまわっている状態が、実は好きなのかもしれません。『やってやろう!』と闘志がわいてくるというか…。やっている最中は、胃が痛いんですけどね。あと、この仕事をやっている皆さん、そうなんですけど、展示ケースを仕上げるのに、1つの作品を作るような思いを込めて作業されていますよね。そこに自分も付いていきたいですし、付いていくだけじゃなくて『やるな』と認めてもらいたい。もちろん、後悔もしたくないですから、今できることを出し切って、作り上げたいと思っています。はたから見たら『そこまでやったらアカンやろ』って世界で、効率が悪いのかもしれませんけど(笑)。でも、そうじゃないと納まらない(出来ない)仕事だということも、わかってもらえたらなぁと思います」。

![]()
日本で何人ぐらい、この仕事をしている人がいるのかなと思うと、すごく特殊な世界ですよね。
根津美術館の仕事は、仕上がったあとも金属部分の工夫が見えるので、ある意味「やった」という達成感があるんですが、佐川美術館とか、青森県立美術館などは、仕上がってしまうと、ガラスしか見えない。やった仕事がすべて隠れてしまうので、淋しいような良い仕事をしたような…。ちょっと複雑です。
たまたま、先週、サントリー美術館に行ったんですが、やっぱり、いいなぁと思いました。自分の関わった仕事は、結構見に行きますね。年数が経ったら、どう変化するのかも気になるので。でも、展示ケースを前にすると、苦労ばっかり頭をよぎって、なかなか作品に集中できないんですけど(笑)。